※相続についての説明はこちらを参考にしてください。
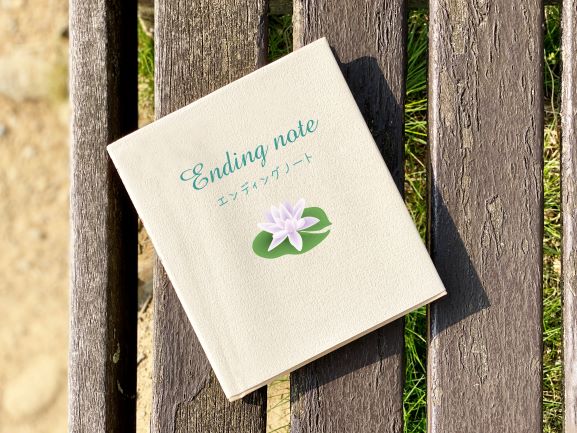
人は、いつか必ず死亡という事実を迎えます。しかし、誰もが自分は「今は死なない。」と思い込んでいます。不慮の事故、病気がいつ訪れるかも知れません。しかし、何歳であっても、もし死亡すれば残された遺族すなわち相続人は悲しみの後、時間がたち冷静になると「遺産相続はどうするか。」という問題に直面します。相続人どうしでもめることもなくすんなり相続ができればよいのですが、もらう財産の多寡によって、その後の相続人の生活に多大な影響をおよぼすことになるとそれが相続人とのあいだで骨肉の争いになったりします。自分の配偶者や子供などの間で争族問題にならないように、生前に遺言を残しておくことをお勧めします。当事務所では、相続・遺言について、いつでも相談を受け付けておりますのでお気軽におたずね下さい。
なぜ遺言書を作っておく必要があるのでしょうか?
1.遺産相続で骨肉の争いを防ぐことができます。
2.事業や家業を特定の子に継承させたい場合
3.夫婦に子がいない場合に、妻に全財産を相続させたい場合
4.世話になった方に財産を相続させる。
以上のような場合は、公正証書遺言書を作っておくことを勧めます。
遺言書を作る前に自分の財産の一覧表を作り全財産を把握します。土地の評価額は税務署で調べます。固定資産評価額は固定資産税の徴収書が市役所から郵送されてきますのでそれを見ればわかります。または市役所へ聞きに行くこともできます。路線価のない宅地は固定資産評価額に国税局長が指定する倍率をかけて算出します。倍率は税務署に行けば教えてくれます。
特に下記のような事情のある方は公正証書による遺言を作り、相続人どうしで争いのないようにしたいものです。
子がなく、配偶者と親又は兄弟姉妹が相続人となる方
「うちには住んでいる家以外にたいした財産もないから遺言なんて必要ない。」とお考えの方には、ぜひ遺言書を作っておくことをお勧めます。
子も両親もいない夫婦の場合、住んでいる家と土地の不動産をを残して夫が亡くなったとします。もし、遺言書がなくて法定相続したとしますと、妻はこの家と土地を分けたら住むところがなくなります。こういう場合は、妻に全財産を残してやり妻が生活に困らないようにするのは夫としての義務ですね。この場合の相続分は妻が四分の三分、亡くなった人の兄弟姉妹は四分の一なります。兄弟姉妹が家と土地の四分の一の権利があるからよこせと言われたら家と土地を売って現金に換えて渡さなければなりません。
さらに、夫の兄弟姉妹がまだ生存中はよい方ですが、他界している場合には夫の兄弟の子(甥・姪)が相続人になります。もし、住んでいる場所が分かればいい方ですが、どこか遠く外国に住んでいるとか、最悪の場合は行方不明になっているとかになると遺産分割協議書の印をもらうこともできなくなり、大変面倒なことになります。こういったことを避けるためにも遺言書を作っておくことを勧めます。
先妻の子と後妻の子がいる場合
先妻の子も後妻との間にできた子も被相続人の子ですので相続分に違いはありません。
子の中に特別に財産を与えたい子(病気・障害を負っている子など)がいる場合
子の中に病気や障害をもつ子がいた場合は、親として子の将来についていろいろと心配になることと思います。このような子に特別に財産を相続させその子の生活費や病気療養費などにあてて困らないようにしてやりたいというのは親としての人情です。
妻に連れ子がいる場合
妻の連れ子がいる場合、相続させるには、養子縁組を行えば実子と同様に相続権が発生します。又は遺言で財産を遺贈します。
相続権のない兄弟姉妹にも相続させたい場合
被相続人に子がいれば、兄弟姉妹に相続権はありません。しかし、兄弟姉妹に親代わりに育ててもらったとか、特に兄弟姉妹にも財産を相続させなければならないような事情がある場合には、やはり遺言によらないと財産を与えることはできません。
子供の嫁に財産の一部を与えたい場合
妻が先に亡くなり同居している子の嫁が被相続人の老後の面倒をよくみてくれたということもよくあることです。このような場合に直接子の嫁に感謝の気持ちを表すために財産を与えたいという場合も子の嫁は相続人ではないから遺言によらなければなりませんでした。
2019年7月1日(施行)から被相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求ができます。
浪費癖の道楽息子・娘に財産を与えたくはない場合
愛人や認知した子供がいる場合
事業やお店など経営している方が、その経営を特定の相続人に相続させたい場合
個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
生前特別に世話になった第三者に遺産の一部を与えたい場合
遺言書作成時の注意
1.相続が複雑な方は、相続人を特定します。相続関係図を作って確認します。
2.相続関係図に相続分を計算して書き入れます。遺留分も記入してみます。
3.遺言は公正証書で作ります。
4.記載は正確に書きます。
5.記載漏れのないように書きます。
6.推定相続人や受遺者が相続人より先に死亡した場合の予備的文言を入れておきます。
7.夫婦相互に遺言書を書いておきます。別々の用紙に書きます。
8.遺留分を考慮した遺言書を書きます。
9.遺言執行者を必ず指定しておきます。
10.葬式費用は預貯金の被相続人名義になっていると死亡と同時に簡単におろせなくなりましたが、2019年7月1日(施行)から預貯金が遺産分割の対象となる場合に各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻を受けることができるようになりました。
11.「相続させる」と「遺贈」するの差異
①相続人以外の者に財産を帰属させる場合は、「遺贈する」、相続人に帰属させる場合は「相続させる」とする
②「相続させる」は遺言者の死亡と同時に遺言分割協議をしなくても特定の財産が特定の相続人に帰属します。
③「相続させる」とした場合は、当該不動産につき、相続人が単独で登記申請できますが、「遺贈する」では受遺者単独でできず、遺言執行者があればその者が、執行者がなければ遺産相続人全員が登記義務者としてその協力を得て双方申請しなければなりません。
④相続人に「相続させる」とした場合不動産登記の登録免許税が1000分の6、「遺贈する」とした場合1000分の25となります。仮に評価額1000万円とした場合、登録免許税が19万円も違うことになりますので十分注意する必要があります。
⑤当該不動産が農地であるときは、「遺贈する」とした場合、受遺者が相続人であっても都道府県知事許可が必要、「相続させる」とした場合はその許可は必要ありません。
遺留分とは何か?
遺留分とは、被相続人が死亡した場合、子又は孫、親と配偶者は一定額の財産を相続する権利です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分はありません。これは、被相続人が遺言書である相続人又は遺贈者に遺留分を超えて過大に遺贈した場合に、減殺を請求できます。これを遺留分減殺請求といいますが、相続開始から又は減殺すべき遺贈があったことを知ってから一年以内に行わないと消滅します。
2019年7月1日(施行)から「遺留分減殺請求」から「遺留分侵割請求」と改められ、遺留分権利者は受遺者(受贈者)に対して金銭の支払を請求できるようになりました。
遺留分の額は
①親(直系尊属のみ)が相続人であるときは被相続人の財産の三分の一
②その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
遺言の種類と特徴
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密に出来る | 遺言の存在、内容共に秘密にできない。 証人から漏れる可能性がある。 | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる。存在は証人から漏れる可能性がある。 |
| 保管の方法 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など | 原本は公証役場、正本と謄本は自筆証書の場合と同じ | 公証人の手元には保管されないので、自筆証書の場合と同じ |
| 紛失、変造、隠匿 | 遺言書があることを知った相続人の1人が自分に有利なように変造したりする可能性がある | 変造、隠匿の可能性はない。 原本が公証人役場に保管されているため、手持ちの遺言書が紛失しても再発行できる。 | 自筆証書遺言と同様に変造・隠匿の可能性がある。 |
| 裁判所の検認 | 事後必要 H20.7.1(施行) 遺言保管所に保管されている遺言については家庭裁判所の検認が必要 | 不要 | 事後必要 H20.7.1(施行) 遺言保管所に保管されている遺言については家庭裁判所の検認が必要 |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 | 2名以上必要 |
| 費用 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 利点 | 自分で手書きして保管するもので秘密も守られ、費用も不要 いつでも書き換えが可能。 | 秘密の保持は十分、偽造変造のおそれは全くなく、効力も問題なることはない。遺言書原本は公証役場に保管されるので、紛失の心配はない。事後家庭裁判所での検認の手続きは不要。 | 公証役場へ提出するので、作成日の特定ができる。費用が公正証書遺言ほどかからない。 |
| 欠点 | 造、変造、隠匿されるおそれがあります。記載について民法で決められた方式に違反したり内容が不明であったりして無効になりやすい。遺言書の内容に相続人の間で不満が出た場合には、本人の自筆かどうか疑わしいとか書いたときはすでにボケていたととかく問題になりやすい。事後家庭裁判所の遺言検認手続きが必要となる | 手続きがやや煩雑で、証人2名必要。公証人への費用が必要ですが、最も活用されています。 遺言公正証書によりすぐ登記ができる。 公証人役場手数料16,000円 | 公証人が遺言内容を確認できないため、記載について民法で決められた方式に違反したり内容が不明であったりして無効になりやすい。証人2名必要。公証されるので費用もかかる。公証人役場手数料11,000円 長所がないのであまり用いられていない |
| 手続きの難易度 | 簡単 | 難しい | やや難しい |
公正証書遺言の要件
1.公証人の面前で遺言の内容を確認する必要があります。入院中で公証役場へ出向くことができないときは、公証人に出張してもらうこともできます。
2.証人二人以上
3.実印、印鑑証明書・戸籍謄本・不動産登記簿などを準備します。
下記の人は証人になれません。
①未成年者
②推定相続人
③受遺者
④これらの者の配偶者、直径血族など
自筆証書遺言書の作り方
(1)民法に定められた方式上の要件をすべて満たしていること。
①遺言書の内容を全部自分で書くこと。
2019年7月1日(施行)から相続財産の目録をパソコンで作成し、通帳のコピーを添付することができるようになりました。
②遺言書作成の日付を必ず書くこと。
③氏名を自署し、押印すること。実印が望ましい。
④加除訂正も方式どおりすること。訂正する場合は厳格に要求されるの で、書き損じた遺言書は破り捨てて書き直す方が無難です。
(2)遺言の内容が明確に特定され、誤解をまねくおそれのない記載をすること
①相続しようとする物件を特定すること。
不動産の場合は登記簿の記載どおりに記載すること。株券は会社名、株式数、定期預金は金融機関名・支店名・証書番号を記載し特定に疑いを生じさせないようにします。マル優などを利用して子供などの他人名義の預貯金は誤解を生じさせるおそれがあるので、十分注意します。
②疑義が生じないような記載内容で、平易な誤解のない言葉で書きます。
遺言公正証書の作り方
1.現在の資産(不動産、預貯金、株券)を洗い出し、一覧表を作る。誰にどの資産をいくら相続させるか案をまとめる。
2.不動産の登記簿を揃える。銀行預金の場合は銀行名・支店・口座番号を特定する。上記の一覧表に記入しておくと整理し易い。
3.遺言の文例集を参考にして、案を書いてみる。
4.案を専門家(弁護士・行政書士)などにみてもらう。
5.証人を二人以上探す。
6.公証役場へ、公正証書遺言の作成日時を予約します。
7.印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)、戸籍謄本、固定資産評価証明書を準備します。登記簿謄本、預金通帳など内容に誤りのないように準備しておきます。
8.公証役場へ遺言の内容と資産の内訳を説明し、費用の概算を計算してもらう。
9.予約した日時に、公証役場へ証人とともに行きます。遺言者は必要書類と実印を、証人は身分を証明するもの免許証と認印などを持参します。必要書類(印鑑証明書、実印、戸籍謄本、相続人以外の場合は住民票、固定資産評価証明書、不動産登記簿、預貯金通帳の金融機関名・支店・口座番号をコピーしたものなど)
10.公証人の前で事前に作成した遺言書の案を口述します。
実務では公証人があらかじめ原案を受け取りこれを公正証書用紙に清書し、証書作成時に読み聞かせ遺言者から「そのとおり遺言します。間違いありません。」という口述を得ます。
11.公証人が書いた公正証書原本の記載内容を確認して、遺言者と証人二人が署名、押印します。
12.公正証書遺言書の正本と謄本を受け取り、費用を払います。原本は公証役場で保管します。
13.正本と謄本は、遺言執行者、推定相続人や受遺者等に預けておきます。
公証人手数料
1. まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
2. 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
②遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
⑤公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
遺言書の検認手続き
自筆証書遺言は遺言保管者が遺言者が死亡した後速やかに家庭裁判所に提出し検認を請求しなければなりません。また、相続人が遺言書を発見した場合も同様です。検認とは相続人に遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言状の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造ほ防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
2020年7月10日(施行)から自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
申立人 保管者または遺言書発見した相続人をいいます。
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
提出書類 申立書(家庭裁判所に用紙があります。または裁判所のホームページからダウンロードできます。)
遺言書
相続人・被相続人の戸籍謄本各1通
相続人利害関係人名簿 1通(家庭裁判所に用紙があります。または裁判所のホームページからダウンロードできます)
申し立て費用 収入印紙 800円
連絡用郵便切手
(1)民法に定められた方式上の要件をすべて満たしていること。
①遺言書の内容を全部自分で書くこと。
②遺言書作成の日付を必ず書くこと。
③氏名を自署し、押印すること。実印が望ましい。
④加除訂正も方式どおりすること。訂正する場合は厳格に要求されるので、書き損じた遺言書は破り捨てて書き直す方が無難です。
(2)遺言の内容が明確に特定され、誤解をまねくおそれのない記載をすること。
①相続しようとする物件を特定すること。
不動産の場合は登記簿の記載どおりに記載すること。株券は会社名・株式数、定期預金は金融機関名・支店名・証書番号を記載し特定に疑いを生じさせないようにします。マル優などを利用して子供などの他人名義の預貯金は誤解を生じさせるおそれがあるので、十分注意します。
②疑義が生じないような記載内容で、平易な誤解のない言葉で書きます。
